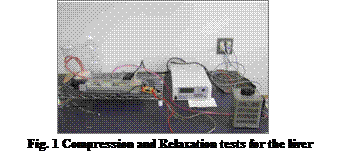
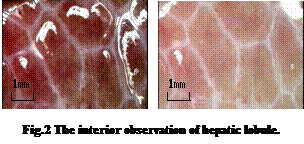
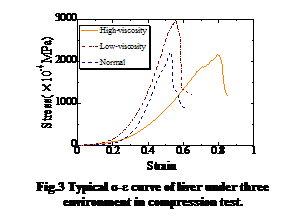
肝臓細胞内の圧縮損傷挙動の解明
Clarification of compression damage behavior in the liver cell
概要 肝臓ガン切離手術の安全性,低侵襲性を高めることを目的とした圧迫型止血器具の開発の一環として,本研究では,圧縮場における様々な条件下での肝臓の機械的性質を調査するとともに,生体内に近い条件での圧縮緩和試験を行い,機械的性質を調査した.また,特殊な圧縮応力下においての圧縮緩和試験,試験片の観察を行った.試験の結果および観察結果に基づき,肝臓の機械的特性にの粘度や総量が影響を及ぼすこと,また,その傾向を明らかにした.
1 緒言
肝臓ガンは現代の食生活や生活習慣の変化によりその発生率が増加しており,社会的に深刻な問題となっている.ガンの完治といった観点から見た場合最も有効な方法として選択されるのが肝切除法である.しかし手術の際,止血に多大な時間と手間を要し,医師および患者にかかる負担が大きくなることが問題なっている.この負担軽減のため,本研究では「圧迫型止血デバイス」の開発に取り組んでいる.肝臓はその他の生体軟組織と同様に,圧縮・段階ともに非線形挙動を示すことが過去の研究成果より明らかにされた.これらの力学的挙動を解明するために本研究では,実験時に試験体に対し血液と同等量の液体を供給するとともに,その条件を生体内に近づけることにより生体内での肝臓の状態に近い力学的挙動を調査した.
2 実験方法
2.1共試体
供試体として屠殺後48時間以内の豚肝臓を用いた.試験に用いる際には生理食塩水(濃度0.9%)を肝臓の門脈及び肝静脈より流入させ,残留している血液を取り除いた後,約w15×t15×h10㎜で内部に直径1㎜以上の血管が存在しないものを肝臓から切り出し実験に使用した.
2.2試験機器
Fig.1に試験機器の様子を示す.試験体を左右からアクリル板にて挟みこみアクチュエータを用い圧縮負荷する.同時に試験体内の微小血管より液体をマイクロポンプを用いて供給した.供給する液体は粘度の違いによる影響を見るため前述の生理食塩水と血液と同程度の動粘度をもつ澱粉を糊化させた液体(濃度1.4%,γ=2.99cSt)の2種類を用いた.
2.3圧縮・緩和試験
試験片を器具内部にはさみ変位制御により圧縮試験を施す.このとき得られた応力-ひずみ線図は,ある応力に達すると応力が急降下する挙動を示した.この最大点を破壊応力σf,この点のひずみを破壊ひずみεfと定義した.また,応力緩和現象を調べるために,一定ひずみを試験体に与え保持することによって,時間ごとの応力を調べる緩和試験を行った.
2.4再圧縮試験
実際の手術において,手術中に止血デバイスを締めなおすことも想定し,圧縮応力下において一定時間後に再び応力を加えた場合の肝臓の力学的挙動を知るため再圧縮する試験を行った.ある任意のひずみ値まで圧縮を加えたときを一次圧縮段階,その後再圧縮するまでの保持状態を一次緩和段階とし,再圧縮・再緩和を行いその過程をそれぞれ二次圧縮段階・二次緩和段階と定義した
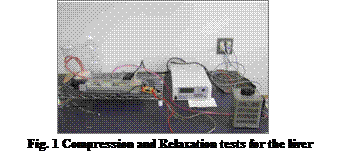
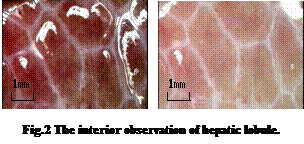
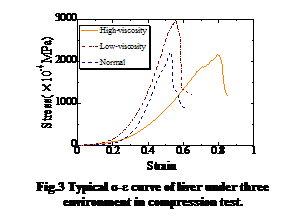
3 試験結果
3.1圧縮試験
Fig.2に試験中の試験片の観察結果を示す.圧縮試験中,何も供給しない場合,肝臓内部の肝小葉には赤い斑点か見られるが,水分を供給することによって,この赤い斑点は取り除かれる.この赤い斑点は肝小葉内部の水分が集中している点であり,水分の供給により内部状態が均一になっている.
Fig.3に圧縮試験により得られた応力―ひずみ線図の一例を,Table 1に試験により得られた破壊応力,破壊ひずみの平均値と標準偏差を示す.液体を供給し肝小葉内部の水分含有量の均一化が行うと破壊応力は上昇した.また,流入させる液体の粘性を増加させた場合には,その破壊ひずみを著しく増加させ,従来のεf=0.5程度からさらに増大し,εf=0.71となった.これにより,肝臓はかなりの変形を加えられても圧縮途中において急激な応力低下を招かないために,従来考えられていた止血デバイスの圧迫量よりも大きくすることが可能である.このとき,以下の式を用いて勾配dσ/dεと応力σの関係は以下の式で表せる.
![]() (3.1)
(3.1)
ここでのAおよびBは肝臓特有の力学特性を表すパラメータである.一般的に式(3.1)は生態軟組織の単軸引張特性を表す式として知られている.肝小葉内部の水分量の不均一を取り除いたときひずみ速度に対して,特性値A, BはFig.4のようになった.次に,マイクロポンプを用いて流入圧力を変化させたときの特性値の変化をFig.5に示す.特性値Aは圧力と共に上昇したが,特性値Bは低下する傾向を見せた.
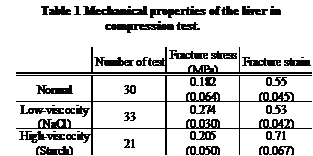
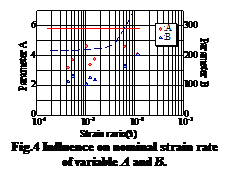
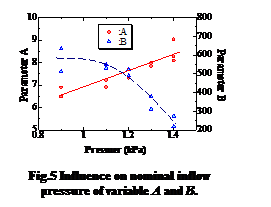
3.2緩和試験
緩和試験結果において,含有水分の不均一を解消した際の初期ひずみによる影響をFig.6 に,ひずみ速度の影響をFig.7に示す.その結果,緩和段階において肝臓は,圧縮時のひずみ速度に影響されず,緩和開始までに与えられる初期ひずみによりその緩和特性を変化させることが明らかとなった.
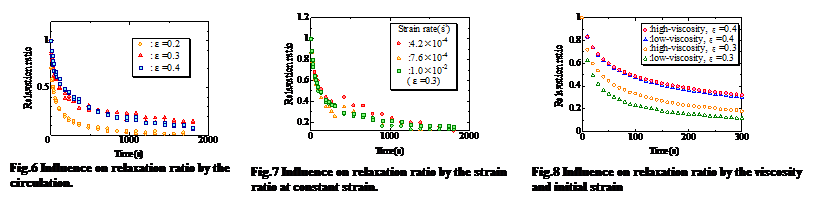
Fig.8に流入させる液体の粘度を変化させた際の初期ひずみごとの緩和率の時間的変化を示す.液体粘度の増大に伴い緩和傾向は緩やかになった.しかし,Fig.6,Fig.8 両者において初期ひずみε=0.4以上を与えたものにおいては緩和傾向の変化はほとんど認められなくなった.これはひずみの増大と共に,試験片内部にある類洞空洞が押しつぶされ,含有できる液体の総量が減ったためだと推察される.これらの結果は,肝臓は圧縮応力下における機械的特性は,内部に含有する液体の粘度および総量が大きく影響することを示している.
Fig.9に流入圧力による緩和傾向の変化を示す.流入圧力の上昇とともに応力の緩和傾向は急になった.応力の緩和は圧縮時に加えられたエネルギを緩和段階での内部含有液体の移動やそれに伴う変形で消費しているため,流入圧力の上昇に伴い肝臓内部における内部含有液体の移動・流出が促進されたためより応力を緩和し易くなったと推察される.
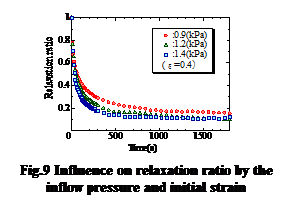
3.3 再圧縮試験結果
Fig.10に一次圧縮段階と二次圧縮段階での圧縮特性を前述の式(3.1)を用いて評価した場合の応力との関係式を示す.二次圧縮段階ではパラメータAの値は非常に小さく0.01以下の値を多くの場合示した.
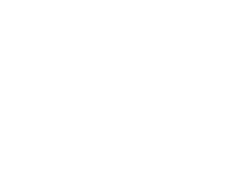
![]()
肝臓は圧縮後ある一定時間保持することにより,含有できる水分量が減少し,内部液体による粘性の影響がほぼなくなるため,弾性体に近い挙動が現れたものと考えられる.
Fig.11に二次緩和段階における一次緩和時間ごとの緩和率を示す.二次圧縮段階では総じて一次圧縮段階よりも緩やかな緩和傾向となった.一次緩和段階の時間T1(s)を変化させたとき応力の緩和挙動はT1=0,0<T1<300,300≦T1,の三つに傾向に分類でき,T1>300sにおいて緩和率の上昇は頭打ちになり収束していった.
Fig.12 に一次緩和段階での試験体の時間ごとの変形率を示す.試験片は緩和開始とともに比拘束方向に収縮した.緩和開始より300~600sの間に試験体の収縮は終了し,その後は約3~4%収縮した状態に留まっていることが明らかとなった.このことより,内部における肝小葉同士の液体移動,および肝臓内部から外部への液体流出はT1=300s前後においてほぼ終了し,生体内の含有液体の移動・流出に伴う応力緩和が抑制される.そのため,T1=300s以以降は緩和率の変化が見られなくなるものと推察される.
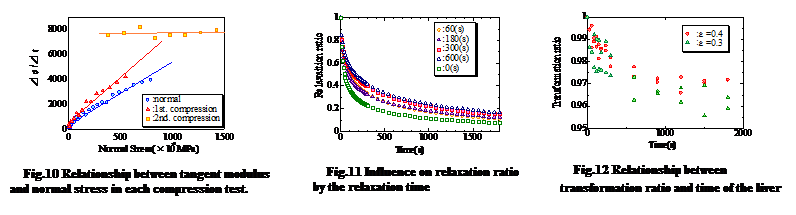
4 結言
肝臓の機械的特性について含有水分の不均一や粘度がその破壊応力,破壊ひずみに影響を与え,応力の緩和挙動は,肝小葉の含有液体の粘度および総量に影響を受けることが明らかとなった.また,止血デバイスを実際に使用するとき,一度締め付けた後,一定時間を置いて再圧縮を行うことが有効である.